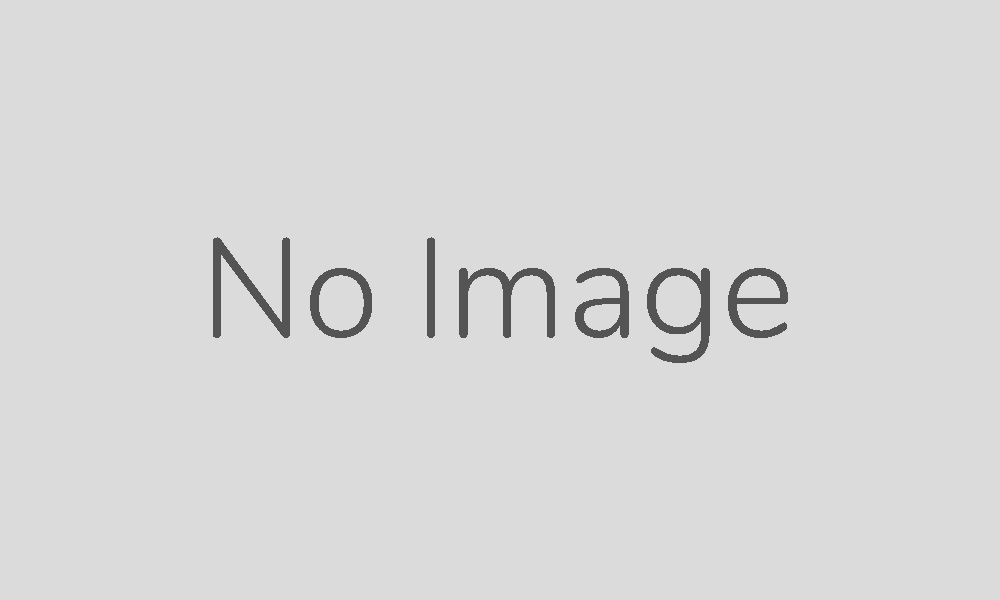森の賢者と騎士 カール・ノエル
森の賢者ーその人はどんな病気でも治せられる、という噂のたっている人物。
その人が今、王都の一角で薬屋を営んでいるらしい。
こんなことがあるとは珍しい、と賢者の伝説をを知っている人は口々に言う。
だって、賢者は普段、どこかの森に住んでいるのだから。
そう、どこかの。
賢者は神出鬼没なのだ。
ある時はアルプス山脈の奥。
そしてまたある時はロシアの森の中、であるとか…。
とにかく賢者の居場所は分からない。
それがどんなからくりをしているかはわからないから余計に怖い。
そんなことを考えながら道を急ぐ。
今日こそはその賢者を見つけるために。
良い情報を聞いた。
賢者が出没する可能性の高い場所や、時間まで聞き出せたのだ。
いや、賢者、ではなく賢者の弟子、らしき人との事だが…。
とりあえず近くで店を営む老夫婦に聞いてみる。
『…という特徴の子を探しているのですが知っていますか?』
「ああ、その子かい。」
「その子なら最近は決まってこの時間に通るわよねぇ。」
「そういえばなんであんなに瓶を持って歩いているのだろうかねぇ。」
「知りませんよ…」
どうやら有名な子なようだ。
でも賢者の弟子がそんな簡単に見つかるわけが…
「あ、あの子だよ。」
え?
わたしは即座に老夫婦が指さす先を見る。
そこには白いフードを目深に被った少年がいた。
それにたくさんの薬品の瓶も持っているし、その他の特徴も合っている。
確かに私が探している子だ。
『ありがとうございました!』
「おぉ、気をつけてな。」
私はその子を逃さないように走り出す。
「そう言えばなんであの子は今日は走っているんだろうねぇ?」
「そんなことをわしに言われても知らんよ。元気ならいいじゃないか。」
待って。
もみくちゃになりそうな人ごみの中を懸命に進む。
少年は意外とすばしっこく、小さいから人ごみの中でもするすると進んでいく。
私が一生懸命走っても追いつけない。
あぁ、足が痛い、それに手も、他のところも冷たくてー
泣きそうな環境。でも構うものか。
私はあの子に聞かなくちゃいけないことがあるんだ。そのことを一心に全力で走る。
待って、貴女に聞きたいことがあるの!
私は声が出ないから叫べなくて、それでもって足も遅くて。結局、私の想いは届かず、その少年は城の門をくぐってしまった。
あーあ。
さすがにあきらめの悪い私でも城の門はくぐれない。
くぐったら何されるかわかったもんじゃないし。
私は
結構一生懸命に走ったからか、かなり疲れた。
…まぁ、あの少年が城の門をくぐれたということは、本当に森の賢者の弟子だ、ってことだし、その事が分かったからいっか。
ここで待ち伏せすればその人が出入りするところに立ち会えるかな…。
なんて思ったが、城には多くの門があるし、秘密の地下通路とかもあるという噂もよく聞く。
あぁ、やっぱり森の賢者に会うことなんて無理だったのかな。
ー本当にそう、思っていた。数分前までは。
先程の出来事から数分。
結局、賢者を見つけることをあきらめきれず、縄文のそばで張り込もうと思い、通行人の邪魔にならないよう、道の端に座っていたが、誰かが私の目の前で歩みを止めたため、私が邪魔だったのかと思い、目線を上げる。
目線をあげたその先には白銀の鎧を身に着けた、優しそうな騎士がいた。
「君、そんなところに座って…寒く、ないのか?」
確かにここは寒い。この道は丁寧に石で舗装されているから寒くないわけがない。
否定の意味を込め、左右に首を振る。
騎士はそんな私の行動を見て少し困ったような表情をしていた。
「こんなところにいたら風邪をひいてしまう。早く帰った方がいいよ。」
騎士は優しい言葉をかけてくれたが、残念ながら私はどこへも行く勇気も、当てもない。
それに、私はこのままじゃ帰れない。賢者に会って私の状態を回復しないと村に帰ってはいけない。そういう約束なのだから。
『心配していだきありがとうございます。ですが私はこの城にいる人に用事があるので帰ることができないだけなのです。』
だから私がそう書いて伝えると、その騎士はまた少し悩んでからこう告げた。
「…用事って何だい?私は一応この城に入れるから君の助けになれると思うんだけれど。」
なんと。
偶然にしてはとても運がいいなぁ。
『森の賢者って知ってますか?』
私のその言葉に騎士は一瞬驚き、納得した様子だった。
「そうか、そういうことだったんだね。」
騎士は私の前にしゃがむと、
「さぁ、立って。賢者のもとに連れて行ってあげよう。」
そうして騎士は元の優しい表情に戻り、私の手を取り、導いてくれた。
騎士に導かれてしばらく城の中を歩く。
正直に言うと、城の中は複雑すぎて大迷宮のようだった。
多分、帰りは一人で帰れないだろうな。と思うほどに。
「ここだよ。」
騎士はその部屋にノックする。
「はいー。どちら様?」
するとすぐに返事が返ってきた。
「アルバートだ。」
ガチャリ。
「アルバ、おかえり。」
その扉から出てきたのは、今日私が必死で追いかけた白いフードの少年だった。
「…アルバ、その子は?」
「本来の仕事をさぼり気味な君へ、プレゼントだ。」
「患者のプレゼントなんて良いものじゃないと思うんだけどなぁ。」
頭を掻きながら
私はそのやり取りを見ながら、鞄から紙とペンを取り出してさらさらと書き始める。
『突然すみません。私はキャロライン、といいます。賢者さんに頼みがあってきましたが、今は弟子のあなたしかいないと聞いているのであなたに聞いてもらてもいいですか?。』
「僕が…賢者の弟子?」
少年は何故か、私のその言葉だけを繰り返していた。
あれ…違ったっけ?いや、でもそういう情報で会っているはずだ。
とっても困惑気に少年は騎士の方をむく。
「アルバート…これは一体?」
「町でそう噂になっているし、実際そうなのでは?」
「うーん。なんか嬉しいような嬉しくないような名前!」
気になったの名前だけなのか!?
この子もちょっと、いや。だいぶ感性の変わった子なんだなぁ。
「で、君は賢者に何を望むんだい?」
『…また、自分の声で歌いたいんです。』
「…は?」
弟子君はぽかんとした表情で私を見返す。
「喋れないのに、話すことじゃなくて歌うことを望むんだ、君は。」
しばらく悩む素振りしていたけれど。
「うーん、僕にとっては謎だな。」
結局理解はされなかった。
まぁ、それだけならいいのだけれど。
「じゃぁ、昔は声が出ていたと、言うことで合っているよね、でもそうすると…」
うなりながら難解な言葉をすらすらとつぶやきながらあーでもない、こーでもないとつぶやきながら部屋の中を歩き回っていてちょっとうるさい。
「紅茶を淹れたんだけど、キャロラインさんも飲むかい?」
どうやら騎士さんはそんな弟子君を気にせずにティータイムの準備をしていたようだった。
ティーカップから立ち上る湯気が心地いい。
「アーロン、紅茶いりませんか?」
騎士が弟子君にそう声をかけても弟子君には聞こえていないようで、まだ独り言を呟いている。
「…アーロン?一旦休憩しましょう。」
騎士は笑顔を絶やさず、しかし目は確実に笑っていなかった。
「あっ…」
その殺気じみたオーラにやっと気が付いた弟子君はやらかしてしまった、という感じだった。
「全く…適度に水分補給しないと大変なことはあなたならわかりきっていることでしょう?脱水症状は死に直接関係するって散々言っていましたよね?だから水分補給をする事は大切なことだって言ったのはアーロン、あなたですよね?…って、私はこの事を何回言えばいいんですか?」
ゴゴゴゴゴという効果音が聞こえそうなぐらいぴったりな怒りようだった。
「頼むから客の前で怒らないで…。」
小さな声で呟くさまは
「これは失礼。キャロラインさん。」
弟子君はふと、唐突に尋ねてきた。
「そういえばなんでそこまで歌にこだわるのさ。別にプロの歌手でもないんでしょ?」
カチンときた。
この言い方、聞き方はないだろう。と思うぐらい酷い。
ティーカップをゆらゆら揺らしながら素っ気なく聞いてくる賢者に少し怒りが湧いてしまった。
『私には歌うことしかないんです!』
プロとかそんな事はどうでもいい。正直これまでの環境が充分な環境だったから。ただ。
『私は歌うことで村のみんなを元気にすることができるんです!だから私は歌うんです!』
毎年、クリスマスの時期に開かれる村の合唱隊の発表会。
いつからだったか忘れたけれど、私はその会の時に歌う事を始めた。
その行事には村人が全員参加していて、私は歌う代表者に選ばれていた。
『キャロラインは歌が上手いよね!』
『 きっと街でも売れる歌手になるわ!』
友達、クラスメイト、死はない人まで。
たくさんの人からこう言われ続けていた。
私は歌うのが好きだった。
だからこの言葉は純粋に嬉しかった。
それに
いつも認められない私を認めてもらえることが幸せだった。
『 皆のために、そして何より、私自身のために。私は歌いたい!』
それが私のただ一つのアイデンティティなのだからー
私は、書き切った。
大切な思いを。
大切な思い出を。
目線を上げて弟子君を見る。
弟子君は書かれた文字をひたすら読んでいた。悲しそうな表情で。
弟子君は紅茶のカップをそっと机に置いた。
「…残念ながら僕ではあなたを助けられない。」
弟子君は冷淡に、残酷に告げた。
『何でですか?さっきまで出来るとか言ってましたよね!?』
「あぁ、言ったとも!しかしその薬を調合し、あげるとも言っていない。」
そんな理不尽な…!
「それに正規の方法できた患者でも無いんだから。他を当たりなよ。」
正規の方法って…
「アーロン、そこまで言わなくても。」
「そもそもね。君は努力したか?そういう話を言ってないだけなのかもしれないけどね?」
弟子君のの口調がどんどん突き刺すものに変わる。
「そもそもその症状は呪いのたぐいだね。しかも誰かが君の幸福を願った方の。」
そして最後に絶望を突きつけた。
「君はこのまま頑張るべきだ。僕にできることはもうない。」
弟子君はぷいと窓側を向いて黙ってしまった。
「ごめんね、キャロラインさん。アーロンはこうなったら譲らないんだ…。」
『いえ。お気になさらず。』
文字の上ではこう、きちんと受け答えは出来たけれど、心はまだ回復しきれなかった。
元々、私の声が治るなんて思っていなかった。
だからだから森の賢者の所に行っても治らない。ということで諦めがついた。
だから声の事はーどうしようもないのだ。
でも悲しかった。諦めないといけないとわかっていてもどうしても辛かった。私の唯一できることを奪われてしまったからー
泣きたくないのに、つい涙があふれる。
「ねぇ、大丈夫?」
大丈夫です、と返したいが先程の賢者の所に、紙とペンを置いてきてしまったらしい。
オロオロしていると
「わっ!」
「ひゃ!」
唐突に驚かされた。
「なんだ。喋れるんじゃん。」
私はー一体?夢を見ているんだろうか?
今、驚いた時に、声が出た!
「夢じゃない、さ。君、名前は?」
「私の名前はー」
一滴の涙
「アーロン、帰りましたよ。」
再びドアが開き、アルバートが部屋に戻ってきたとき、僕は、まだ一人で大粒の涙を流し、泣いていた。
そう、一人で。
僕は正直、あの回答でよかったのかがまだ、自信を持てない。
『作れないことはないが、作らない。』
色々それらしい理由をつけて、自分の最適解を押し付けて。そして彼女を追いだした自分は。正しかったのだろうか?
「アーロン、本当は彼女のこと、本当は、助けられるんじゃないんですか…?」
唐突に言われたその言葉を聞いた瞬間、つい体を震わせてしまった。
あまりにもその言葉が、今の自分が考えてい事だったからだ。
確かに助けられる。森の小屋まで行かなくても材料ならそろっている。
本当に、自分なら助けられるのに、僕は彼女を助けなかった。
「アーロン、今なら間に合いますよ。」
その言葉がどれほど甘く、魅力的に聞こえるか。きっと彼には分らない。
「アルバートは黙っていろよ。お前は何にもわかってないんだから…!」
つい、一人叫んでしまう自分がいた。
いつもはこんなことはならないのに…今日は人が悪かった。
なんて言えたらよかったのに。その言葉すら出ずに、状況を悪化させるだけの感情的な、毒を含んだ言葉しか出ない。
「お前はいいよな、その人が幸せになろうが関係ないし。賢者に付き添っている騎士、ってだけだもんな。」
僕は賢者、薬剤師、または魔術師とも呼ばれている。
しかしそれは1種の差別用語だ。
僕は正常な人間じゃない。
「彼女は人魚の末裔だぞ?彼女は異常だったんだ!」
あぁ、こんな言葉を使うつもりはなかった。
そう後悔しても、もう遅い。
一度、声に出してしまった言葉は変えることはできないのだから。
「…」
思わず絶句している彼を見ていたらその言葉を発した僕でさえ苦しくなってしまって。
「…ごめん。」
「アーロン!」
僕はアルバートの静止の声を振り切って隣の部屋に逃げ込んだ。
『彼女は人魚なのだから。』や、『 異常』。
これらの言葉は彼に送る言葉の中では最上級の嫌味だ。
だって、彼もそういう存在に近い、人造人間だから。
ーまぁ、僕自身にとっても嫌味だ。僕は死ねないから。
そんなことは分かりきっていたはずなのに言うとは。
不必要に人を傷つけたくなかったはずなのに。
ーまた涙が流れ落ちる。
せめて、人間の心がある間はー人間だと自覚している間は幸せでいて欲しい。
それが、僕が叶えられなかったこと、そしてすべての人間にあるべきことだと信じているからー。