森の賢者と騎士
森の奥深くには賢者がいる。
その賢者は、宮廷の魔術師だという噂があり、どのような病気でも治せるだとか、動物と話せるのだとか、嘘か本当も分からないような伝説がたくさんある人だ。
そんな凄い有名人なのだが、誰もその賢者の顔や名前すら知らないらしい。
唯一の手がかりは賢者が住んでいると言う噂の森の場所のみ。
この賢者が本当に存在するのならきっと謎の病で二ヶ月ほど昏睡状態にある幼馴染みのアリサを目覚めさせられるのではないか。
最後の希望である、森の賢者に会うべく、俺は森に入った。
ここまではよかったのだが…。
森で迷ってしまった。
しかも帰り道も分からない。
俺は方向音痴でもなく、森などに入っても迷った試しがないから迷わない自信があったが、かえってその事が仇となったようだ。
先程まで暖かく照っていたはずの太陽がいつの間にか雲に隠れていた。
とりあえず一息しようと、近くの木にもたれ掛かる。
風が木々を優しく揺らす。
さわさわとその流れに合わせ音を奏でる。
そういえばここに来るまでに全く人に動物にも会わなかったなぁ、と考えていたら、急に近くの茂みが動いた。
人なのだろうか?
そうだといいのだけれど。
ガルルルル…
「ひっ…。」
正体は人間ではなく、野生の獣だった。
あ、絶体絶命のピンチ。
音は次第に早くなりながら近づく。
俺はただ、絶望するしかなかった。
あぁ、きっと俺はここで終わるのだろう。
親友も救えずに…、無様に…。
最後にそう思い、目を閉じた。
しかし、いつまでたっても痛み、苦しみは訪れない。
逆に不安になり、そっと目を開ける。
すると目の前には、白銀の鎧を身につけた一人の騎士が立っていた。
「君、大丈夫?」
「は、はい。」
「ならいい。」
騎士はそう言い、獣に近づく。
「この子は敵じゃない。どうか鎮まってくれないか。」
騎士が優しくそう言うと、獣はなぜか警戒を解き、去っていった。
よかったぁ。
「あ、あの!ありがとうございました。」
「森には危険な獣が多く生息している。
次からは注意した方が良いだろう。」
と言い、騎士は森野出口の方向を教えてくれた。
「まって!」
「何だい?」
「賢者って、あなたの事ですか?」
騎士は賢者というワードを聞いて驚いた。
いや、でも実際は兜を被っているから表情は分からないのだが。
「…君は賢者にどういったものを求め、利用する?」
「俺はただ、昏睡状態の親友を救うべく、薬を会いに来ただけだけど。」
騎士はしばらく黙っていた。
「ついておいで。」
騎士はそれだけ言い、俺の手を握って歩き始めた。
森をしばらく進むこと十数分。
これまで変わること無かった並木道が終わり、森の開けた場所に辿り着く。
そこには小さな小屋があり動物たちも集まっていた。
「ごめんね。」
騎士はその集まっているところを横断し、小屋へ一直線に向かう。
「ここだよ。」
近づいてみると意外と大きいログハウスのような建物だった。
「失礼します。」
カランカラン…。
ドアの呼び鈴が気持ち良さそうな音を出す。
しかし小屋にはいっても誰もいなく、ただ大小様々な小瓶や、薬草やハーブらしきものが干してあった。
「アーロン?いないのかい?」
騎士はやれやれ、と言いながらカウンターの奥の部屋に入っていった。
そして騎士はまたひょいとあらわれ、君はこの椅子に座って待っているといい、といって入っていった。
俺はその指示通り、椅子に座って待つことにした。
正直、建物に遭遇できずゆっくり休めないし、森をたくさん歩きすぎて疲れたのだ。
「アーロン!いい加減に起きなさい!」
騎士の大声がこのとなりの部屋まで響く。
「うるさいなぁ…。」
「アーロン…?」
「あぁもう!起きればいいんだろ!?
今日は一体何なんだよ、いつもは起こさないくせに!」
「だからぁ!お客さんだって出掛けるときから言っているだろう?」
「わかった、わかった!
だから布団はがすな!」
何だかやり取りを聞いていると、とある親子の日常のように思えてくる。
少し待っていると扉が開き、一人の人がやって来た。
「お待たせいたしました。今日はどのようなご用件でしょうか?」
丁寧に言うこの言葉は、明らかに大人の言動だ。
しかし見た目がどう見ても13歳を越えているとは思えないのだ。
年齢だけでなく、髪や目などのパーツも逸脱した色で、肩らへんまでのびている髪の毛は白銀、肌は白く美しく、瞳はまるでライラックのようだった。
「おーい。あんた生きてんの?」
「アーロン、失礼じゃないか。」
「いや、でもさぁ。なんも言われないとね?」
ちなみに寝起きだからなのかは分からないが、Tシャツにパーカーをはおり、カジュアルなズボンをはいていた。
「あー、もしかして僕の見た目にビビった?」
「いや、そういうことじゃなくて。」
「あ、なんだ!話せるのか!」
「話せますよ!?ただ綺麗だなって思っただけで!」
その少年はにこりと笑ってこういった。
「なんだぁ。子供みたいな見た目だからバカにされたのかと思ったよ。」
少し人間離れした見た目をしているが基本的には楽しそうな人柄だった。
でもどうしてそのような外見なのかはきっと聞いてはいけないことなのだろうと察し、深く聞かないことにした。
「で、君はだれ?」
「俺はアルト。近くの町からやって来たただの一般人だ。賢者とは君のこと?」
「いかにも。賢者というより、ただの薬剤師、アーロン。こっちは幼馴染みのアルバート。僕はあいつのことをアルバって呼んでる。」
「あの、普通に騎士さんでいいですよ。」
騎士、アルバートさんは少し恥ずかしそうにそう言った。
「アルバってその鎧と同じように頭固いの?そこはさぁ友達風にいっておこうよ。」
「いっておこうよって…。アーロンに言われたくないです。」
「ところでアルバ、いつになったらその暑苦しい鎧を脱ぐんだい?」
「…」
「ほらほら。」
「…」
アルバートさんは黙る。黙ったまま。
しかし観念したのか、ようやく口を開く。
「…仕方ないですね、襲われたときは全力でアーロンを盾にしますよ。」
「ははは、冗談きついなぁ。」
「骨は拾ってやりますよ。」
そう言い、アルバートさんが扉の向こうに消えて行った。
「ふう、やれやれ。やっと向こうへ行った。あ、そういえばアルトは僕をさがしに来たんだよね?一体どいつが欲しいのさ。」
「どのような病でも治る薬が欲しいです。」
「あぁ、そいつ。」
アーロンは急につまらなそうな反応を返してきた。
「アルト、君はそんな重い病気とか、余命数年とかの人には見えないんだけど。」
「…この薬は自分で使わないんです。」
「…え?」
アーロンは、急にこちらを振り返り興味深そうに聞いてきた。
「どうして?誰のためにこんな危険な場所まで来たんだい?
「俺の親友、アリサが昏睡している原因はきっと俺にあるんです。俺がしっかりしていなかったから守れなかった。だからです。」
「へぇー。アルトの親友ねぇ…。意外と深い話じゃないか。」
ふーん。と、アーロンが勝手に納得した後、
「で、アルトは何者なの?」
「ただの一般人なんですけど…」
「そういうことじゃなくてさ…」
まいったな…どう説明したらいいのかとブツブツ言う。
そしてその言葉は紡ぎ出された。
「今回のアリサって子と…一体どんな関係なのさ。」
「…というと?」
「アリサって子、恋人?っていうか、婚約者なの?」
「!?」
まだ告白もしてないし伝えてもいない。
それに結婚前提とか全く無い。
そもそも幼馴染みだ。そんはなずはない。
「図星ってところか。」
「いやいやいや。ただの幼馴染みで…」
「嘘だな。」
間髪いれずにそう突っ込まれる。
「アーロン、からかうのは止めなさい。言っていいことと悪いことがあるでしょう!?」
その時、アルバートさんが戻ってきた。
アルバートさんははちみつ色の髪に若草色の瞳をした人だった。
「ちぇ。邪魔すんなよ…。」
「あの、話の内容、聞こえてますからね?こちらの部屋まで。」
「げ。」
あなたはなんでいつもこういうことをするのですか、などという笑顔だが目が笑っていないかおのアルバートさん。
説教だけ勘弁して、という顔のアーロン。
両者にらみあう。
勝った方は言うまでもない。
「アーロン、貴方はいつもそうです。そろそろ世界の理ぐらい覚えてください。礼儀がなってません。それにあなた冷蔵庫に入っていた私のアイスクリーム食べたでしょう?まだ言ってくれたらよかったのです。アルバ、君のアイスクリーム美味しそうだったから食べちゃったって。でもあなたはいつまでたっても言わない。親しき仲間にも礼儀ありです。今度は三倍おごってください。あと…」
…相当長い説教が、始まってしまった。
ガミガミと怒ると長いタイプのアルバートさんと、ひぃぃぃと、いう感じで縮んでいるアーロン。
そして俺は喉が乾いたのでお茶を飲んで痴話喧嘩(?)を眺めることにした。
「…とまぁまだ言いたいことはたくさんありますがお客さんの前なので一旦ここまでで終わりとしましょう。」
「よかったぁぁ。」
「アルトさん帰ったら続きやりますからね。」
「勘弁してよ。」
崩れ落ちるアーロン。
自業自得だからしょうがない。
けれど、アイスクリームとかなんでも、食に関わる恨みはひどいって言うから気をつけて、アーロン。
「さて、アーロン。」
「はいはい。」
さてと、とアーロンが言い、空いている小瓶に透明な液体と透明な液体を入れて混ぜる始める。
「僕は君がこの薬をうまく扱えると信用できた。だからこれを持っていくといい。」
コトリと、先程の透明な液体が入った、小さなひとつの瓶が目の前におかれる。
「これがすべての病が治る薬。」
「…これが。」
「気を付けるといい。その薬ひとつで国を動かせる力だからな。」
国ひとつを…
「アーロン、久しぶりに賢者らしいこと言いましたね。」
「アルバは黙ってて。」
「はいはい。」
アーロンは小瓶をゆらゆらさせてまたもや続ける。
「その薬はそれだけあるけれど、全部飲ませてはいけないし、飲ませ方も注意して。下手な飲ませ方したら…死ぬよ。」
それから俺は薬の使用上の注意と管理のしかたを教わった。
すべて教わり帰ろうとすると、外は日が沈みかけていた。
「アルバート。」
「分かっている。さぁ、森の出口まで送ろう。」
アルバートさんはそういってから案内してくれて、森を抜ける一歩手前で止まった。
「もしこの薬のことで困ったらまたここに来るといいですよ。今度はアリサさんと一緒に来てくださいね。きっとアーロンも待ってますから。」
「何年か経つかもしれませんが…また行きます!」
「えぇ、そのときまでお待ちしていますよ。永遠に。」
もちろん。またきっと会えると信じている。
「それでは、またのお会いを楽しみにしています。」
騎士は手を振る。
俺は久しぶりに帰って来た人里を見た。
アリサが待っているあの町までいけばー
彼女の笑顔が待っている気がした。
番外編
全ての病を治す薬
「これでよかったんですか?アーロン。」
「あぁ。これでよかった。」
渡した薬は全ての病を治せられる物ではない。
アルトが望んだ、彼女だけに効く薬。
「きっと彼女が起きたら彼は幸せになる。だってそれはアルトが望んだことだから。」
しかしこれだけではない。ということはアーロン自身がいやと言うほど知っている。
「だけどアルトが人間である限り、きっと全ての病に効く薬を悪用してしまうんだろうね。それが変えることのできない定めだ。」
それは、この場に居た誰にとってもすべてが幻想のように楽しかった出来事。
賢者も騎士にも忘れられない大切なもの。
しかし彼らはただの人間ではない。
年を取れない呪いにかかり、いやと言うほど生きた賢者とその幼馴染みの人造人間の騎士が営む不思議な薬屋の物語。
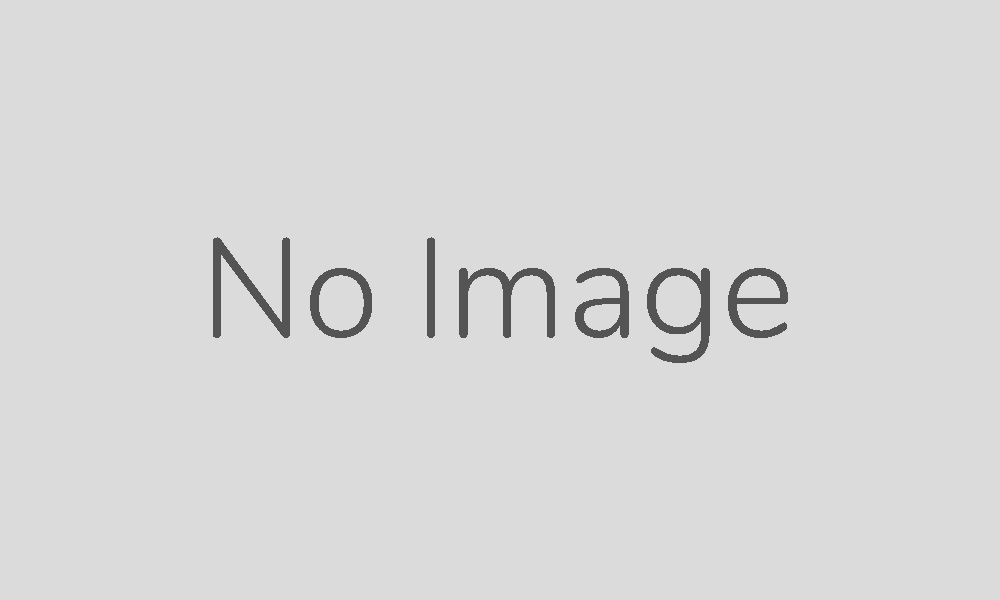
コメント